こんにちは、ちゃんわです。
この記事では、中山競馬場 芝2500mの条件で開催されるG1、有馬記念について解説しています。
以下の方におすすめです。
- 有馬記念がどのようなレースになるのか予想するための参考情報が欲しい
- 他のメディアでは紹介されていない有馬記念のデータが知りたい
- 有馬記念でどのような馬を狙うのが良いか検討する材料が欲しい
それでは、早速解説していきます。
開催概要
開催情報
まずは開催情報についてです。

基本の重量は57キロ、牝馬は-2キロです。
3歳馬も-2キロで、斤量面では少々3歳馬が有利です。
開催状況
開催回は第5回の8日目となっており、12月から始まる中山開催はすべてCコースで実施されております。
冬の時期ということもあり、芝の生育はほぼなく使う分だけ傷んでいく状況となっています。
ですから、12月の中山のAコース8日目ともなると、4コーナーや直線の芝はかなり内側の状態が悪くなっていることが多いです。
冬の時期はダートのレースを多くしており、なるべく芝の傷みを軽減するようにJRAの馬場造園課も努力をしていますが、この時期はどうしても厳しくなっているのが現状です。

有馬記念の特徴
有馬記念はG1の中でも、グランプリと呼ばれるレースです。
グランプリレースとは「ファン投票によって出走馬が決定されるレース」で、春シーズンは宝塚記念、冬シーズンは有馬記念の2つがグランプリと呼ばれています。
ファン投票で10位以内に選出された馬は優先出走権を得ることができ、その他は普段と同じく獲得賞金の上位から出走できることになっています。
有馬記念は年末の大レースということもあり、普段競馬を見ないような層も参加する人が多いお祭りレースとなっています。
有馬記念に関するローテーション
次に、有馬記念に参戦する馬のローテーションについて解説します。
各陣営がどのようなレースを使って有馬記念に向かうのかを図で表現しています。

有馬記念へのステップとなるレースは大きく分けて3種類あります。
G1ローテor凱旋門賞 組
G1ローテor凱旋門賞出走の馬は有馬記念でも最有力となる存在です。
よくあるローテーションパターンは以下の5つです。
- 天皇賞(秋)→有馬記念の間隔開けた秋2戦ローテ
- 天皇賞(秋)→ジャパンカップ→有馬記念の王道秋3戦ローテ
- 叩き→ジャパンカップ→有馬記念の3戦ローテ
- (叩き→)エリ女→有馬記念の牝馬ローテ
- 凱旋門賞→有馬記念の外国挑戦ローテ
基本的にはこのG1ローテ組がほとんどになります。この組から中山芝2500mの有馬記念に向く馬を見つけるという予想がセオリーになってくると思います。
かつては、海外帰り初戦は調整が難しく好走可能性が低いと認識されていましたが、最近ではそんなことはまったくなく、凱旋門賞出走馬を始めとして海外帰りの馬でもしっかりと有馬記念に向けて調整して出走します。
そのため、凱旋門賞帰りの馬も日本のレースでは最有力候補となるため、しっかりと精査が必要です。
また、最近では秋G1を3戦するローテを各陣営控える傾向があります。
秋3戦でも初戦はG2等のいわゆる叩きレースを使っている程度で、秋にG1を3戦して有馬記念で好走というローテは他馬比較でも余裕がなく厳しい結果になっています。
有馬記念にギリギリの状態で出走する馬よりもしっかり回復してフレッシュな状態で望める馬を狙うのが良さそうです。
また、牝馬組ではエリザベス女王杯組もかなり有力です。
牝馬限定戦でもかなりレベルが高く、好走した馬はもちろんですが、展開や馬場が向かなかった馬にとっては穴になりうる存在となります。要チェックです。
他重賞 組
次に他重賞組です。
先程「有馬記念に出走する馬はほとんどがG1ローテだ」と記載したようにこちらの他重賞組は出走間隔が短かったり、適距離でない馬が多くなる傾向があります。
- ステイヤーズSが勝利→スタミナ活かしたいので有馬記念
- アルゼンチン共和国杯勝利→距離適性がありそうだから有馬記念
- マイルCSで好走→もう1戦させるなら有馬記念
このような馬が出走してくるイメージです。
確かに2016年はアルゼンチン共和国杯勝ち馬のゴールドアクターが勝利しましたが、それ以外の馬が勝ったケースは近10年ではなく、かなり珍しくなります。
逆に、この組でG1常連組に勝てる馬を見つけることができれば、高配当が期待できます。
3歳路線
3歳路線は基本的に菊花賞のみとなります。
近年、3歳馬は菊花賞だけでなく、天皇賞(秋)に向かう馬やジャパンカップへ向かう馬が増えてきました。
それでも唯一の3歳馬路線である菊花賞組は、スタミナを要する有馬記念との親和性が良く、3歳がゆえの斤量の恩恵があり更に有利です。
菊花賞で、中団からしっかりと追って差し切る強さを持った馬が好走する傾向がありますが、斤量が有利な条件となるので展開と相談しながら狙うのがおすすめです。

2016年までは金鯱賞が12月の第1週に開催されていたために金鯱賞から有馬記念のローテーションが存在していましたが、現在は3月に移動したためありません。
グラフを見るとわかるように大半がジャパンカップ、エリザベス女王杯、天皇賞秋、菊花賞というG1が並んでいます。
有馬記念のレースの流れ
まずは、2012~2021年のレースラップをグラフで見てみます。

有馬記念は2500mのレースのため、1F目は最初の100mのタイムが計測されています。
グラフが少し見にくくなるので、最初の100mを除いたレースラップのグラフも御覧ください。

特徴ごとに分類して解説します。
前半で13秒以上のラップを踏むような超スローペース(2014年,2016年,2017年)

基本的に13秒以上のラップを踏むレースは前半の1000mのタイムが61秒を超えるケースが多いです。
この場合、暮れの中山で馬場が荒れるとは言え前が残りやすい展開になります。
相手関係(逃げたい馬が複数いるか、それとも単数か)や逃げ馬の性質を考えて超スローペースになると予想される場合は前を徹底的に狙ってみましょう。
中山の直線は短いため、差し追い込み馬が上がり最速の脚を使っても前の馬には届かないケースがあります。
ただし、2014年は前半がスローペースで先行馬が勝利したものの、2,3着には差し馬が入りました。これは、3~4コーナーでマクリが入ったことによる後半のペースが一気に上がったからと考えられます。この年はゴールドシップを始めとして、ウインバリアシオンやラキシスといった馬が一気にペースアップしたことで流れが変わりました。
前半が超スローペースになると予想されるレースでは、以下の2点を考慮して予想を組み立てましょう。
- 逃げたい馬が複数いないか
- 道中でまくってくるタイプの馬がいないか
比較的緩いペースだが、後半で一気にペースが上がる(2015年,2020年)

ペース自体は早くありませんが、13秒を踏むようなことはなく、前半は淡々と緩いペースが続きます。
しかし、8F目あたりから一気にペースが上がっていきます。後方に実力上位&スタミナのある人気馬がおり、このままのペースだと届かないと判断した騎手が一気にスパートを仕掛けてくるからです。
2015年だとゴールドシップ、2020年だとクロノジェネシスが該当します。
どちらも1番人気かつスタミナ豊富な馬で、ロングスパート戦に持ち込もうとします。
この場合に狙うべき馬は、以下の3点
- ペースアップに対応できる馬
- ペースが上がっても内でじっとできる先行馬
- ペースアップに一切付き合わず、最後の直線に賭ける追い込み馬
1つ目はペースアップを仕掛けてくる人気馬に対応できるレベルの馬を狙うという点です。これは実際には人気馬になってしまいそうです。
2つ目、ペースアップ時についていこうとするとどうしても外を回ることになりロスが増えます。そのロスを避けるために内でじっとできる馬を狙うという方法があります。これは先行馬でかつ内ラチ沿いを確保できる馬という条件になるので、人気薄の馬にもチャンスがあります。
3つ目は、ペースアップに付き合わずとも終いの脚で間に合う自身のある馬です。
一瞬の脚に賭けるので少々ギャンブル要素は増えますが、これも面白い戦法になります。2020年の例だとサラキア(2着)、2015年の例だとトーセンレーヴ(6着)のような戦法になります。
比較的締まったペースで流れる(2012,2018年)

次は、先程のようなスローペースのレースではなく、前半から比較的締まったペースで流れる展開になる場合です。
逃げ候補が複数いる場合や、逃げ馬のスタートが良くないタイプでスタートしてしばらく隊列が定まるまで時間がかかる場合、前半が締まったペースになりやすいです。
隊列が決まるまでの前半に先行馬は体力を使ってしまいますので、最後のスパートで先行馬が後ろの馬に飲み込まれる可能性がでてきます。
こうなると、2012年はゴールドシップやルーラーシップ、2018年はレイデオロやシュヴァルグランのように追い込みが決まりやすくなりますね。
- 常に上り3F上位の脚を使っている追い込み馬
前半が速くなる(2019,2021年)

最後に前半がかなり速くなるパターンです。
2021年のパンサラッサ、2019年のアエロリットのように、大逃げを仕掛けてくる馬がいる場合、レースラップはあまり参考にならなくなってしまいます。
気にするべきは、大逃げ馬から離された実質逃げ馬のような形になる馬の動きに注意が必要です。
2019年の実質逃げ馬は13番人気のスティッフェリオで、早めに仕掛けていったため、直線は後方からの追い込み馬に差されてしまう形になりました。
この場合は、前の馬に仕掛けられてもあまり怖くないため、直線で一気に溜めていた脚を開放できるタイプの馬が有利になります。
一方で、2021年の実質逃げ馬は4人気の菊花賞馬タイトルホルダーで、比較的強い馬が捕まえに行ったため、そのタイトルホルダーを目標にしている中団の馬が上位を占める形になりました。
この場合は、実質逃げ馬を物理的に捕まえられるような位置(中団あたり)で競馬ができる馬を狙うべきでしょう。
つまり、実質逃げ馬の実力によって、道中の位置取りや、ラストスパートの位置が変化するということになります。
- 実質逃げ馬の実力が劣る→上がりの速い追い込み馬
- 実質逃げ馬の実力が優る→実質逃げ馬を捕まえられる中段あたりの馬
まとめ
以上のまとめを行います。
有馬記念は、年末最後の祭りレースで秋のG1を盛り上げた馬の集大成のようなレースです。
また、グランプリレースということもあり、レースの展開も様々存在します。
出走馬と想定される位置取り、作られるペースをベースに狙う馬を探していきましょう。
- 基本はG1ローテor凱旋門賞組から。他重賞から狙える馬が入れば高配当
- G1ローテ組でも、G1を3連戦はキツい。叩き→G1を2戦か、秋G1の2戦目が有馬記念の馬が良い
- 想定されるペースパターンは4つ。「超スロー」「後半一気にペースアップ」「締まったペース」「前半速い大逃げがいるレース」
- ペースパターンによって狙い馬を選び分ける!(狙い馬はそれぞれの章に記載)
以上、有馬記念の予想のポイントでした!
皆さんの予想の参考になれば幸いです。

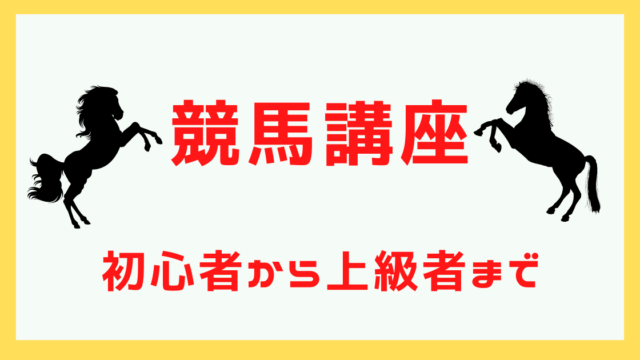





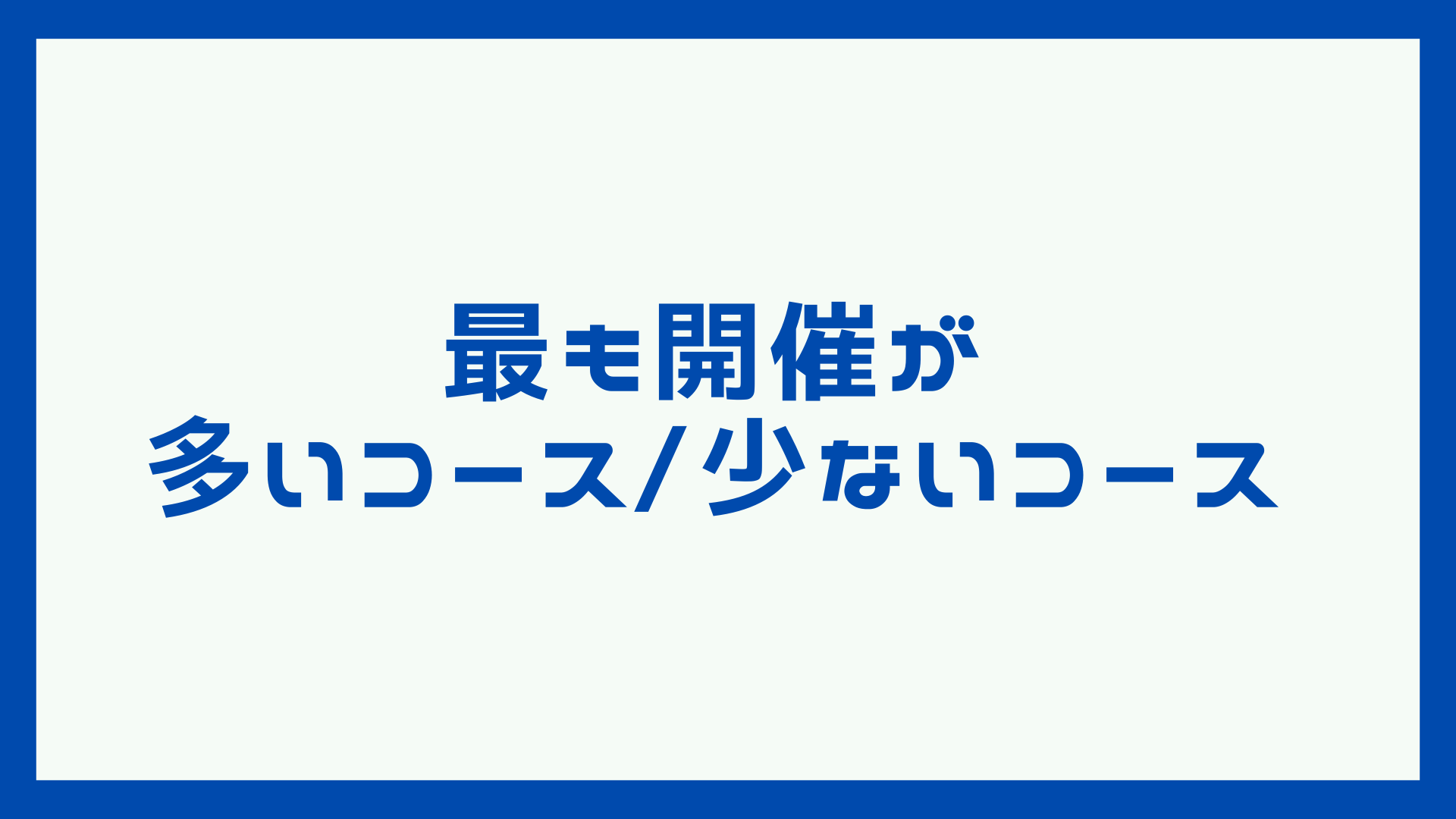

コメント